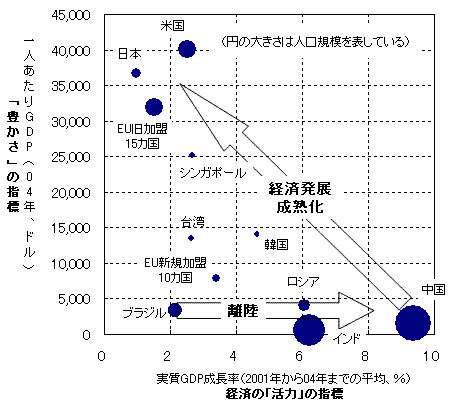| ダイヤモンド・ホームセンター 2006年8-9月号掲載 |
| 企業として、中国とどう向き合うか |
|
世界の生産拠点から巨大成長市場としての存在へ 中国とどう向き合うか? 日本の長い歴史のなかで常に重要な意味合いを持ち続けてきた、古くて新しい問い掛けである。その答えは、双方の変質や国際情勢の変動に応じて変化し続けてきた。このことは、今日の日本企業にとってもあてはまる。急速な経済発展と構造的な変質を続ける隣の大国は、多くの日本企業にとって、ますます存在感を強めている。 近年の推移を振り返ってみると、日本企業にとっての中国の存在感が急速にクローズアップされたのは、中国の経済発展が本格化してきた1990年代前半のことである。当初の段階では、中国は、低廉な労働力の存在を背景とした商品生産拠点としての位置づけで、世界中の注目を集めた。生産拠点としての中国へのアプローチは、通常の商品輸入から、中国の製造業者に生産を委託する開発輸入、さらには自社工場の開設とさまざまであった。 この時期の成功事例として特筆されるのは、やはり“ユニクロ”を展開するファーストリテイリングが構築した、中国の生産者を組み込んだサプライチェーンの成功だろう。同社では、信頼できる委託生産先を発掘・育成するとともに、商品の企画から店頭に並ぶまでの日数を極限まで切り詰めるSCM(サプライチェーン・マネジメント)の仕組みを構築することで、低価格で品質の高い商品を的確に市場に投入することを可能にした。その結果、消費者から圧倒的な支持を得て、日本のリーディングカンパニーの一社に数えられるまでに飛躍したのである。その他にも、電気機械やアパレルなど、労働集約的な生産プロセスを有する業種の企業の多くが、中国を商品調達や生産の重要な拠点と位置づけ、中国での事業を展開していった。 それに続く次の段階では、世界各国の企業にとっての生産拠点としての存在感が大きくなるにつれて、中国の経済規模、所得水準も向上し、世界各国の企業から、巨大な成長市場として位置づけられるようになってきた。実際に、都市部を中心に自動車や家電製品、高級衣料品などの市場が拡大していった。市場としての中国に対しても、商品輸出から販売チャネルの構築、自社店舗の展開と、多彩なアプローチが採られた。 リテールビジネスでは、マクドナルドやケンタッキーなどのファストフード・チェーン、さらにはカルフール(仏)、ウォルマート(米)、テスコ(英)、メトロ(独)といったリテール先進国の大手企業が店舗を展開していった。1990年代に自国内の収益環境が極端に悪化した日本のリテーラーは出遅れる形になったが、2000年代に入ると、コンビニエンスストアの大手3社や、厳しい競争を生き抜いてきたGMS(総合スーパー)の二強、イオンとイトーヨーカ堂が事業展開を本格化させてきている。 顕在化した中国事業のリスク 重要な生産拠点として、また巨大な成長市場として世界各国の企業から注目を集める一方で、中国での事業展開にかかわるリスクも浮かび上がってきた。その契機となったのは、2003年のSARS(重症急性呼吸器症候群)禍であった。中国でSARSの感染が広がったことで、中国からの物流が一時的にせよ途絶する可能性が生じたのである。 このときには、結果的には全面的な供給途絶というような深刻な事態は避けられたが、中国からの部品や商品の供給に依存していた企業は、そこに大きなリスクが存在していることを認識させられた。それを受けて、中国以外にも供給拠点を確保しておこうという「チャイナ・プラスワン戦略」が提唱され、自動車や電気機械メーカーを中心に、中国以外のアジア諸国にも供給拠点を持とうとする動きが広がった。 さらに2005年には、小泉純一郎首相の靖国参拝問題などを背景に、北京や上海など中国各地で反日デモが相次いで発生し、中国に展開した日本企業の工場や店舗の一部が操業停止に追い込まれた。SARS禍が浮き彫りにしたのが中国に限らず事業展開を特定の地域や分野に集中させ過ぎることにともなう普遍的なリスクであるのに対して、反日デモの発生は、日本と中国の関係から生じる固有のリスクといえるだろう。 また中国経済自体にも、今後の企業活動に影を落とす材料が目立ってきている。まず、経済の急速な発展に人材の供給が追いつかず、一部では人材の引き抜き合戦が生じるほどで、全般に人件費が高騰しはじめている。人材の質は向上しつつあるといわれてているが、生産拠点としての大きな魅力であった人件費の安さは、次第に失われつつある。 加えて、工場による環境汚染の問題や、労働者の人権を無視した苛酷な労働実態の問題がクローズアップされ、すべての企業に環境と人権に配慮した体制を整えることが求められるようになってきた。これは、中国で生産活動を行ったり商品を調達する日本企業にとっても、コストアップ要因となる。 そしてもう一つ、中国の経済発展の阻害要因として深刻に受け止められているのが、石油をはじめとする天然資源の世界的な需給逼迫の問題である。2004年後半から本格化した原油価格の高騰は、巨大な人口を有する中国が急速な成長を続けていることが大きな要因となっている。石油をはじめとする資源価格の高騰は、世界経済全体を冷え込ませることになるが、中国自身にとっても、エネルギーの利用効率の低さもあって、成長を阻害する要因として効いてくるものと考えられる。 深い関与が求められる状況に 経済の発展プロセスの入口に立ったばかりの中国は、所得水準は低いものの急速な成長を続けており、経済の成熟化の結果として高所得ながら成長力を喪失した日本とは対照的な状態にある(下図)。
13億人という巨大な人口と、日本が失った旺盛な成長力を有する中国は、ネガティブなファクターが顕在化してきた今日でも、日本の企業にとって、依然としてきわめて重要な存在であることに変わりはない。とはいえ従来のように、単に低廉な労働力や巨大な市場を取り込もうとするだけの事業展開では行き詰る可能性が高い。中国での事業活動を持続的に発展させていくには、従来とは違った新しい展開が求められる。 中国を生産拠点として位置づけるうえでは、圧倒的な低コストに期待するのではなく、相対的にコストの低い事業環境下で、いかに高品質、高付加価値の商品を生産するかという方向性が主流になるだろう。そこでは当然、単なる商品調達ではなく、中国企業と密接な関係を築いたうえでの開発輸入や、人材の養成も視野に入れた自社工場の開設といったアプローチが前提となる。 また、今後大きな進展が予想されるのが、環境や資源など、中国が抱える国家的な重要課題の解決に、事業活動を通じて貢献するアプローチだ。環境と資源の問題は、2006年にスタートした中国の政策運営の基本方針である第11次5カ年計画においても、持続的な発展に向けた重点課題と位置づけられている。加えて、中国の環境、資源の問題は、中国のみならず世界規模の問題である。ことに地理的に隣接し、資源に恵まれない日本にとっては、他人事ではすまされない重要な問題と位置づけられる。 そうした大きな問題に対して、日本の企業としては、エネルギー効率が高く環境への負荷が小さい工場やインフラの建設、環境関連技術、省資源技術の移転、さらには省エネ志向の商品やサービスの提供といった形で貢献することができるはずだ。日本企業がそうした貢献を続けていくことは、中国の人々の反日感情を緩和させ、日中関係から生じる固有のリスクを軽減することにもつながるだろう。 いずれにしても、これからの中国事業においては、中国の産業や経済、社会に対して深く関与していくことが必要になる。中国は日本企業にとってきわめて奥行きの深いフロンティアであり続けるだろうが、そこへ挑んでいく企業には、従来にも増して強固な意思と高度な戦略性が求められることになるだろう。 関連レポート ■世界経済の成長の構図−「新興国主導」の実相− (三井物産戦略研究所WEBレポート 2012年12月18日アップ) ■2010年代の世界の動きと産業の行方 (三井物産戦略研究所WEBレポート 2011年3月18日アップ) ■世界経済の構造転換と新興国の牽引力 (三井物産戦略研究所WEBレポート 2010年6月11日アップ) ■新興国経済の成長力 (三井物産戦略研究所WEBレポート 2010年3月8日アップ) ■「豊かさ」と「活力」と−成熟化経済と人口大国の行方− (The World Compass 2006年2月号掲載) ■2006年の世界地図−「多元化」で問い直される日本の外交戦略− (読売ADリポートojo 2006年1-2月号掲載) ■原油価格高騰−静かに広がるインパクト− (読売ADリポートojo 2005年12月号掲載) ■2005年の世界地図−混沌のなかから浮かび上がる新しい構図− (読売ADリポートojo 2005年1-2月号掲載) |
|||||
| Works総リスト |