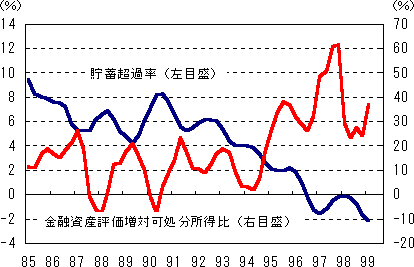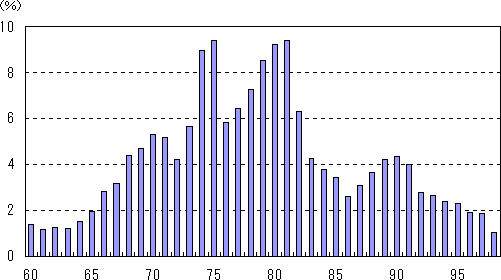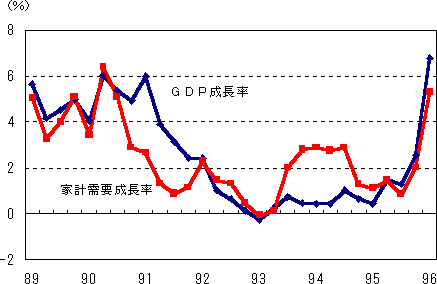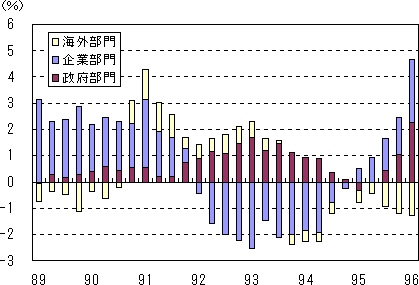| リテールバンキング(経済法令研究会)1999年10月号掲載 |
| 米国経済 快走が止まるとき−バブル末期の日本との対照− |
|
快調に走る米国経済。その快走は、いつ、どのような形でストップするのか。いまや世界経済の唯一の牽引車となっている米国経済の動向は、米国のみならず、世界経済全体にとって最大の関心事だ。 米国経済は、昨年後半あたりからオーバーヒートの印象が強まってきた。ところが、オーバーヒートとなれば当然出てくるはずのインフレ再燃を示す動きが、これまでのところ、ほとんど現れていない。こうした状況は、米国経済にとっては、過去に経験のないものだ。今、米国経済は、過去に例のない「未知の領域」へと踏み込んでいる。 しかし、その様子は、1990年代初頭の日本経済の転落をつぶさに見てきた者にとっては、「いつか来た道」のように思えてならない。資産市場の活況と家計需要の膨張、国家財政の健全化と金融セクターへの信頼感。当時の日本経済と、現在の米国経済の間には、さまざまな符合がある。 本稿では、米国経済が「未知の領域」へ踏み込んだプロセスを改めて整理するとともに、今後の展開について、バブル末期の日本の経験を下敷きに、検討してみたい。 1.「未知の領域」への道程 (1) 株価と家計需要のスパイラル構造 まず、需要サイドでオーバーヒート感のもっとも強い家計部門の動向をみてみよう。このオーバーヒート感は、98年に家計貯蓄率がほぼゼロにまで落ち込んだところで、急速に高まった。しかし、家計の可処分所得のうち、需要として顕在化しなかった割合を表す「貯蓄超過率(=(貯蓄−実物投資)/可処分所得)」でみると、95年頃から既にその徴候は現れている(図表1)。そして、96年の後半以降は、貯蓄超過率はほぼゼロとなり、稼いだお金をすべて消費や住宅投資に使い切ってしまう状況が続いている。 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
その背景に持続的な株価の上昇があることは容易に想像がつく。事実、80年代以降、家計部門では、株式や投信、個人年金などの金融資産の評価増と、貯蓄超過率の間には密接な関係がみられる(前掲図表1)。97、98の両年には、家計部門の金融資産の評価増額は可処分所得の4割を超えている。95、96年も3割前後だ。この値が年間で3割を超えたことは、データの揃う50年代以降一度もなかったが、年収の3割、4割といった儲けが何年も続けば、収入を割いてお金を貯めようという気持ちが薄らいでも無理はないところだ。 株価の上昇は家計需要(消費、住宅投資)を拡大させ、家計需要の拡大は景気を、そして株価をさらに押し上げる。株価と家計需要がそれぞれの動きを相互に増幅させあうスパイラル構造が形成されたのである。では、こうした構造は、いつ、どのようにして米国経済に組み込まれたのだろうか。まず、株式市場の方の要因としては、将来の成長期待や競争力を「理論的」に折り込んだ投資手法が、コンピュータの普及にともなって、実戦投入されてきたことがあげられる。また、家計部門の方をみると、投信や個人年金、さらにはディスカウント・ブローカー、オンライン・ブローカーの成長によって株式が大衆化したことで、株価と家計行動のリンケージが強まったことが関係しているだろう。 これらは、いずれも80年代の半ば頃から本格化した現象だ。したがって、前述のスパイラルは、今回の拡大局面において初めて、その威力を発揮したと考えられる。ただ、それには、もう一つの条件が必要であった。それは、供給サイドの問題だ。株価と家計需要のスパイラル的な拡大も、供給がついてこなければ、インフレと金利の上昇によって抑え込まれてしまう。しかし、今回の拡大局面では、これまでのところ、そうした状況にはいたっていない。いったい何が起こったのだろうか。以下、供給サイドに目を転じてみよう。 (2) 供給制約の緩和 今回の拡大局面は、前の時代に比べて、きわめて物価の安定した時代であった(図表2)。60年代後半以来、四半世紀にもわたって米国経済に根付いていたインフレ体質は「物価は上がるもの」という人々の思い込みによるものであった。この「思い込み」が、今回の拡大局面初期の'Double Dip'あるいは'Jobless Recovery'と呼ばれたほどの極端なスロースタートによって払拭された。長期にわたる「インフレなき景気拡大」の基礎が固まったのである。 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
その後、景気は徐々に野に入ってきた。この時期にインフレを抑え込む要因となったのは労働生産性上昇率の向上である。労働生産性の上昇ペースは、96年からの3年間には明確に加速している(図表3)。その要因としては、IT(情報技術)の活用が急速に進んだことがあげられている。産業別の統計でみても、ITを効率化に結びつけやすい商品流通の分野(卸売業、小売業)が労働生産性向上の主役を担っている様子がうかがえる。 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
しかし、成長ペースはさらに加速し、98年の後半には、失業率が4%台前半にまで低下した。従来、5%を切ればインフレが再燃する危険地帯だと考えられてきたことを考えると、現在の米国経済は、既に限界を突き抜けてしまった状態といえるだろう。それでもなお、インフレは抑え込まれている。過去の経験則は覆された。これをどう考えればよいのだろうか。この問いに対しては、現時点で確答することはできないが、仮説として、いくつか拾ってみよう。 第一の仮説は、単に失業率が下がっただけでは、多くの労働者が賃上げを勝ち取れる状況になるとは限らないという考え方だ。近年の生産性向上は、情報機器の装備強化と並行して、新しい技術体系への移行にともなう企業間の機能分担の最適化が進んだことで実現してきた。アウトソーシングや、活発なM&Aによる企業の分割、統合の動きも、機能分担の最適化の一側面として捉えられる。そうしたなかでは、労働者の賃金は、能力や成果に応じて、きめ細かく決定されるため、全体としての労働需給が逼迫しても、全般的な賃上げには結び付きにくいと考えられる。 また、機能分担の最適化の過程では、より効率的、より低コストで機能を果たせる企業に仕事が回され、効率化、コスト削減に遅れをとった企業は仕事を失い淘汰されていく。企業は低賃金の労働力の活用を心掛け、高賃金の労働力をできる限り節約しようとしている。そうした企業努力の結果、需給のミスマッチで就業できなかった人々が戦力化されている。そのため、失業率は低下しているものの、限界的な労働力需給の逼迫感は高まっていないという見方もある。 第二の仮説は、世界的な供給過剰の状況が、米国一国のインフレ圧力を押し止めているという考え方だ。実際に輸入が拡大しているというだけでなく、海外の供給力が潜在的な競合相手となっているために、賃金、物価ともに抑制されている可能性がある。 この仮説の背景には、為替の安定という条件がある。経常赤字の拡大にともなってドル安が進むようであれば、輸入物価の上昇だけでなく、海外製品との価格競争が緩和されることで、国内物価も上昇しやすい環境になる。ところが、98年の赤字拡大に際しては、それまでのドル高こそストップしたものの、ドル安基調にはならなかった。米国経済の好調さゆえに、資金の流入が順調だったためだ。裏返せば、世界全体としての供給過剰の環境下では、需要の好調な国は、順調な資金流入によって為替レートを維持できるため、供給制約を受けにくいということだ。 2.調整局面のシナリオ (1) 調整局面への入口 現在の米国経済は、供給制約が緩和するなかで、株価と家計需要のスパイラルが働き、従来では考えられなかった高みへ達した。問題はこれからだ。供給制約が緩和したとはいっても、失業率の低下にも経常赤字の拡大にも限度がある。インフレ再燃、金利上昇、需要後退というストーリー自体が消滅したわけではない。 また、家計需要が自律的に後退に向かう可能性もある。株価の上昇ペースが鈍れば、家計部門は再びお金を貯めはじめる、裏返せば、需要を抑えるようになると考えられるからだ。 ここで重要なのは、株価が「下がる」場合に限らず、「上がらなくなる」場合も含まれるという点だ。つまり、現在の株価がバブルではなく、完全に定着したとしても、水準調整的な急上昇が納まった段階で、家計の貯蓄超過率は従来の水準へ向けて上昇しはじめる。その過程では、家計部門の需要の伸びは所得の伸びを下回り、一転して景気の足を引っ張ることになる、という筋書きだ。 調整局面への入口が、インフレの再燃であっても、需要面で最初に影響が現れるのは家計部門だろう。金利の上昇は株価の上昇にブレーキを掛け、家計需要の調整を促すと考えられるからだ。既に、長期金利は上昇に転じ、株価も踊り場状態にある。このまま株価が頭打ちになれば、家計需要の調整は、来年の前半にもスタートするだろう。最終的には、貯蓄超過率でみて、近時の▲1%程度から5%あたりまで、累計で6%ポイントに及ぶ大幅な調整も考えられる。この場合、仮に3年かけてゆっくり進んだとしても、その間、年2%ずつ家計需要を落とす要因となる。経済成長率に対しては、年1.4%のマイナス要因だ。 そうなると、今度は所得の伸びも鈍化する。設備投資も今のペースは維持できないだろう。さらに、それが株価を押し下げるようなことになれば、家計の貯蓄超過率の調整はさらに加速され、需要の減速は相当深刻なものとなるだろう。 (2) バブル末期の日本との対照 ここで思い出されるのが、90年代初頭、バブル末期の日本の状況だ。当時の日本の、資産市場の活況とそれを背景とした家計需要のオーバーヒートは、米国の現状とオーバーラップする。図表4は、当時の日本のGDPと家計需要の実質成長率を示したものである。これによると、90年の末から、経済全体の減速に先駆けて家計需要が減速しはじめている。それを追う形でGDPの成長率も91年半ば頃から低下し、それがさらに家計需要を落ち込ませる形で、GDPと家計需要はスパイラル的に落ち込んでいった。 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
家計需要が先行して減速していったのは、資産市場の活況を受けて水膨れしていた部分が、金融環境の変化による資産市場の停滞にともなって剥落していったたためである。日本の場合、土地が主役を演じたという点では、米国と異なっている。しかし、資産市場の停滞が家計需要の調整を招くという流れそのものは、前に述べた今後の米国で想定されるシナリオと共通するものだ。 その後の展開を素直に考えると、最大の需要セクターである家計の需要が減速すれば、当然、経済全体の減速につながるはずだ。しかし、日本のバブル末期には、家計需要が減速しても、半年間は経済の成長ペースは落ちていない。これは、家計需要と同時に、輸入にも急ブレーキがかかったためだ。90年末には、経済成長率に対する海外部門(輸出−輸入)の寄与はプラスに転じている(図表5)。 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
これと同様の現象は、米国でも期待できる(これは当然、米国の需要に依存している他国の経済にとっては好ましくない事態ではあるが…)。日本の場合と同様、家計需要が減速しても、経済の拡大ペースは、半年程度はキープできるだろう。その過程で、現在、きわめて高い水準にある経常赤字は縮小に向かうことになる。 経常赤字の縮小は、家計部門の貯蓄超過率の再上昇とあわせて、米国経済全体が、オーバーヒートの状態から通常の状態へ回復していく動きであり、避けることのできない「調整局面」と捉えることができる。問題は、この調整が、深刻な不況への導入部となるのかどうか、ということになる。 3.不況は避けられるか (1) 頼みは政策対応 調整局面において、輸入の減速による下支え効果があるといっても、日本でもそうだったように、それには自ずと限界がある。加えて、家計需要の減速が鮮明になれば、企業の設備投資も抑制される可能性が高い。 現在の米国企業の設備投資は、IT関連の独立投資(景気に左右されない設備投資)が中心で、少々需要が伸び悩んでも減速しにくいといわれている。しかし、同様の説は、バブル末期の日本でも流布していた。IT関連のほか、労働力不足や環境問題に対応するための投資がさらに拡大すると考えられていたのである。しかし、その期待は裏切られ、設備投資は急速に落ち込んだ(前掲図表5)。 これは、米国でも同じだろう。独立投資の比率が高まっているとはいっても、需要増に対応した投資も依然として相当の割合を占めている。それが落ち込むだけでもインパクトは大きい。また、企業収益の伸び悩みが投資の拡大を抑えるということも考えられる。そうなると、家計需要の調整は、日本の場合と同様、不況への導入部ということになってしまう。あとは、何らかの政策対応に期待するほかない。 バブル末期の日本の場合、この局面で政策対応を誤り、深刻な不況に陥ってしまった。90年代初頭の日本の財政は、長期にわたる景気拡大を経て急速に健全化していた。最悪の場合、財政出動で不況は回避できると考えられていたし、事実、その余地は十分あった。そのあたりも現在の米国の状況に通じるものがある。そして、そうした状況だったにも関わらず不況の到来を避けられなかったという事実は、今後の米国経済を見通すうえで、心に留めておく必要があるだろう。 日本では、経済成長率が減速しはじめて間もない91年8月には、第一弾の公定歩合引き下げが実施された。政府需要が景気を押し上げはじめるのも比較的早く、91年末頃からだ。それでも不況を回避するには遅すぎ、規模も小さ過ぎた。この時点で、家計需要の調整幅を埋め合わせるだけの規模、おおまかに見積もって累計10兆円程度の財政支出拡大を実行していれば、深刻な不況は避け得たと考えられる。これは相当大きな額であるが、その後の経緯を思い起こせば、その程度であれば、むしろ安いものだったといえるだろう。 ただし、これはあくまでも、早い段階で思い切った財政投入を行っていれば、という話だ。しかし、当時の世間の雰囲気を思い出してみると、企業も家計も、バブル期の行動を反省する気分で、とても大型の景気対策を実施できる風向きではなかった。加えて、地価の引き下げへの要請が強く、景気対策を求める一部の声はかき消されてしまった。景気後退が鮮明になってからも、景気対策と地価抑制というジレンマのなかでの政策運営は、結局、後手後手に回ってしまったのである。 (2) 正念場を迎える米国の状況 日本の経験は、正確な状況認識と、それを踏まえた迅速な政策対応ができていれば、深刻な不況を回避できた可能性を示唆している。その意味で、米国は早晩、正念場を迎えることになるが、情勢はいささか複雑だ。 危機感の薄さという点では、かつての日本と大差なさそうだ。しかし、ここで、来年に控えた大統領選挙が大きな意味を持ってくる。正確な状況認識に基づく危機感ではないにしても、今年後半から来年にかけては、政府が景気対策に敏感になる時期だ。これが、結果的に吉と出る可能性がある。 ところが、それに水を差しかねないファクターもある。株式市場が、政府の経済への介入を嫌っているという点だ。財政支出の拡大や金融緩和は、市場の不信感を招き、かえって株価を押し下げる可能性がある。そうしたジレンマのなか、政府の打てる手は限られてくる。現政権の経済政策の、市場志向あるいはウォール街志向のスタンスを考えると、このファクターの意味は重い。財政支出拡大や金融緩和が使えないとなると、考えられるのは減税しかないが、減税策は、タイミングが遅れると、需要を押し上げる効果が落ちてくる懸念がある。 4.不況、その後 調整局面を不況の導入部としないための経済運営は、きわめて困難なものとなるだろう。となると、不況に陥ってしまった場合の展開についても、ある程度考えておくべきかもしれない。 日本では、93年初頭に底入れした後、家計需要は伸びを回復したものの、経済全体は、ほとんどゼロ成長のままで推移した。結局、家計需要も再び減速し、本格的な回復は96年までお預けとなった(前掲図表4)。 これは、企業の設備投資の回復がまったくみられなかったためであるが、その背景には、回復期の主役となるはずの中小企業に対する銀行の融資姿勢が変化したことがある。地価の下落によって巨額の不良資産を抱えてしまった銀行は、リスクの高い中小企業向けの融資を絞らざるを得なかったのである。 景気の後退と地価の下落はスパイラル的に進行していった。そして、地価の下落の悪影響は、銀行部門に集中して現れた。巨額の株式含み益を背景に磐石にみえた銀行部門が、一気に弱体化したのである。その結果、経済を支えてきた金融システム、リスク負担の枠組みが土台から崩壊してしまった。 これと同様のことは、米国でも起こるのだろうか。家計需要の調整が不況を招いてしまえば、ハイペースの経済成長を前提に上昇してきた株価が一転して大幅に下落することは避けようがない。その場合にも、日本の場合と違って、金融部門への影響は軽微だという見方が強い。 しかしその反面、米国の株価下落は、家計部門を直撃することになる。将来に備えるための金融資産の目減りは、家計需要を冷え込ませるだけでなく、人々の間に不安や不満を高めることにもなりかねない。金融不安は避けられても、何らかの社会不安が起こる可能性があるということだ。先般、アトランタで起きたデイ・トレーダーによる銃乱射事件も、その予兆とも呼べる現象かもしれない。 また、米国では、経済的に成功して富を築いた人々が、ベンチャービジネスへの出資者として、次世代のビジネスを育てる役割を担ってきた。株価の下落は、そうした富裕層の資産を目減りさせ、その枠組みを損ねる可能性がある。それは、米国社会の最大の長所である経済のダイナミズムを根幹から揺るがしかねない。 これらは、もはや景気云々の問題ではない。より多面的な検討が必要になるだろう。とはいえ、今の段階でそこまで考えるのは、先読みが過ぎるというものだ。何しろ、足元の米国経済は絶好調だ。今しばらくは、米国の実体経済と株式市場の動向を慎重に見守っていくことにしよう。 関連レポート ■新たな局面を迎えた米国経済 (The World Compass 2006年7-8月号掲載) ■旧論再検討(1)米国経済編−ハズレた悲観論− (Views text025 2005年2月2日) ■米国経済は巡航速度に向けてソフトランディングへ−「貧困層」の存在がダイナミズムの源泉− (商品先物市場 2004年11月号掲載) ■「貧困の輸入」で活力を維持する米国の消費市場 (チェーンストアエイジ 2004年4月15日号掲載) ■経済の活力をどう確保するか−世界に広がる「貧困エンジン」のメカニズム− (読売ADリポートojo 2003年12月号掲載) ■米国経済−繁栄と貧困と− (The World Compass 2000年10月号掲載) |
|||||||||||||||||||
| Works総リスト |