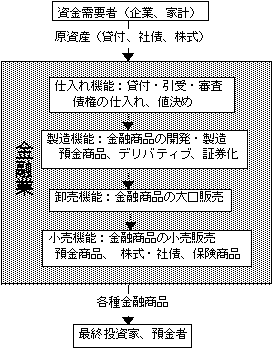| 週刊金融財政事情 2000年10月9日号掲載 |
| サービス産業への進化を模索する金融業 −「三つの‘C’」で顧客の信頼を獲得する戦略を− |
|
(本稿に関しましては、掲載稿のファイルが手元にないため、オリジナルの原稿をアップしています。特に、「9.おわりに−淘汰と競争の時代ー」の章は掲載段階ではカットされておりますが、ここでは筆者の考えを明確にするため、そのままの形で載せさせていただきました。) 1.はじめに−サービス産業への進化− 二〇〇〇年に入り、日本経済の復調は次第に鮮明になってきた。しかし、今後数年間は、あらゆる産業、企業、個人が、新しい時代環境に適応するための調整期間ということになるだろう。もちろん金融業も例外ではない。というよりも、時代の変化への適応がもっとも必要なセクターとさえいえる。 従来の金融業は、産業の育成役、決済機能の担い手、といった意味で経済全体のインフラと位置付けられ、競争制限的な規制で保護されてきた。しかし、資金制約の緩和にともない、産業の育成役としての金融業の地位は、ベンチャー・キャピタル、総合商社、コンサルティング・ファームなどと並ぶ一プレーヤーに過ぎなくなってきた。また、情報技術の進歩によって、資金決済サービスの高度化と、それにかかわる諸機能のアンバンドリングも可能になっている。これらの結果、金融業のインフラとしての性格は弱まり、保護的な規制の必然性は薄らいだ。 今、金融業は、顧客ニーズを第一に考える「サービス産業」への進化が求められている。インフラとしての位置付けゆえに、規制の枠組みのなかに安住してきた金融業にとって、この変化はきわめて重大だ。 もちろん、現実に規制が緩和されるかどうかは、規制当局の判断次第である。しかし、企業、個人両セクターからの幅広い要請と、マクロの視点での必然性があれば、最終的には、それらが当局を動かし規制緩和を促していくはずだ。 そこで本稿では、国民全体のニーズに沿った規制緩和は当然進むものと仮定したうえで、サービス産業としての金融業がどのような変貌を遂げていくのかを展望してみたい。 2.金融と商品流通の対照 金融を単なる資金の流れと捉えると、金融セクターは、資金を流すパイプ役のイメージになる。これは、インフラとしての金融業のイメージだ。それを、資金の流れと表裏をなす金融資産の流れとして捉え直してみると、また違ったイメージが浮かんでくる。個別の投融資(=原資産)ごとに固有のリスクとキャッシュフローが、金融セクターを経由する間に、さまざまに加工、変換され、金融商品に仕立てられて流通していくイメージだ。 サービス産業としての金融業を考えるには、この捉え方の方が適している。それは、金融資産の流れとして捉えた金融の枠組は、一般商品の製造・流通の仕組みとまったく同じ構造であり、一般商品の流通と比較、対照することで金融業を捉えなおすことができるからだ(下図、注1)。 |
||
|
||
基本的な構造が同じだといっても、流通システムのなかでの役割分担の仕組みは、商品によってさまざまに異なっている。その違いは、食品にしろ衣料品にしろ、商品ごとの特殊性に応じた合理的な理由があって生じたものである。また、その仕組みは固定的なものではなく、技術の進歩や顧客ニーズの変化にともなって進化を続けている。 その意味では、金融業においても、金融商品という商品の特殊性に応じて、その流通形態が成立したのだといえる。ただ、これまでは、さまざまな規制によって、時代の変化に応じた進化の道を閉ざされてきた。 そう考えると、金融業がサービス産業へと進化していくプロセスを展望するうえでは、前掲図の捉え方をベースに、他の商品の流通や販売の仕組み、あるいは、その進化の歴史と対照させてみることにも意味があると思われる。 注1.前掲図のような捉え方は、株式や投信などの場合には馴染みやすい。しかし、預金商品の場合には、理屈はともかく、感覚的には馴染みにくい。それは、預金商品に、他の金融商品や一般商品と決定的に違っている点があったためでもある。 かつては、護送船団方式の枠組みの下、特定の銀行が破綻した場合にも、その資産・負債は他の健全銀行が引き継ぐことが暗黙の前提であり、預金者にツケが回されることはあり得なかった。これは、商品流通との対照でいえば、素材の良し悪しが商品の優劣にまったく反映されないということだ。通常の商品ではあり得ないことである。 しかし、護送船団方式が崩れ、ペイオフ凍結が解除されれば、預金商品の信用リスクに、金融機関ごとの格差が生じる。そうなれば、預金についても商品格差が生じ、商品流通と同様の構造を持つことになる。 3.家電流通のアナロジー 現状の金融商品の流通システムの特徴は、素材の仕入れから製造、販売まで、それぞれの金融機関が一貫して行い、各金融機関が提供できるのは自社で製造した商品に限られるという点にある。これは、一般商品でいえば、かつての家電製品の流通とよく似た構造だ。 家電の場合には、小売り段階はメーカーによって系列化された電器店であって、メーカーそのものではなかったが、事実上、各メーカーが自社商品の流通をほぼ完全に掌握していた。しかし、この体制は消費者に親切なものではない。 ビデオでも冷蔵庫でも、買うときにはいろいろなメーカーの製品を比較しながら、どれにするか決めたい。しかし、メーカーの系列店しかなければ、消費者は、いくつもの店舗を回らないと、どれを買うか決められない。これでは不便だ。家電量販店が台頭してきたのは、価格の安さもさることながら、各社の商品を比較検討して購入できる場を提供したことも大きい。家電販売の主役は、今や完全に量販店に移っている。 金融業においても、家電量販店のような方向性は有望である。金融業の場合には、複数のメーカーの商品を揃えるというよりも、預金、株式、公社債、投信、保険といった、さまざまなタイプの金融商品を比較、検討して購入できる業態が想定される。 現在では、家計の資産規模の増大や長寿化の進行にともなって、家計セクターが金融業に求める機能は大幅に拡大してきた。そのニーズは、単なる資産運用にとどまらず、資産面を軸とした人生設計のサポートにまで及んでいる。それに対応するためには、金融商品を総合的に品揃えした業態は不可欠であり、そうした業態こそが、金融業の進化形ということでもある。 4.目指すは「ワンストップ・ソリューション」 金融業の進化形のコンセプトは、資産の面での人生設計のサポートを総合的に提供することにある。多岐にわたる顧客ニーズの特定の領域を包括的に充足させるという考え方は、より普遍的な表現でいえば「ワンストップ・ソリューション(以下、OSS)」ということになる。 OSSの実現によって顧客を惹きつけている業態としては、前述の家電量販店の他、住宅関連の領域でのホームセンター、主婦の日常の買物という領域での食品スーパーなどがあげられる。また、コンビニも、「仕事や学校からの帰途にその日に必要なものを買い揃える」というニーズに応えた業態であり、やはりOSS型の一つといえる。 近時のサービス産業の動向をみると、OSS型の業態が、顧客ニーズを満たしきれない零細専門店や、対応すべきニーズの特定に失敗した百貨店、GMS(総合スーパー)などの大型総合業態を圧倒するという傾向が、一段と顕著になっている。また、OSS型の業態であっても、バラエティ・ストア化したホームセンターや、カジュアル衣料にまで手を広げた食品スーパーなど、OSSの本質を踏み外してしまった企業は、軒並み業績を悪化させている。 これは、消費者向けのサービスに限らない。企業向けサービス業においても、ITをはじめとする技術体系の変革や、コア事業への集中、アウトソーシング推進の流れのなかで、さまざまなOSS領域の設定が試みられている。 今後は、金融業においても、OSS型の業態に進化を遂げた企業が、進化できずに零細専門店的な業態にとどまっている企業を圧倒していくだろう。 従来の金融業のように、自社商品しか販売できないのでは、優秀な人材がいかに誠意を持って顧客と接しても、そのニーズには応えようがない。多くの金融業の営業担当者が、歯がゆい思いをしてきたはずだ。OSS型業態への進化は、営業担当者が実力に応じて活躍できる体制の構築にもつながる。 5.主力は消費者向けの金融OSS OSSの視点に立つと、金融業の事業は、決済関連サービスの領域と、資金・財務面を軸とする企業活動サポートの領域、そして一般消費者の資産計画サポートの領域と、大きく三つに区分される。 そのうちの決済関連サービスの領域は、それ自体を一つのOSSの対象と捉えてサービスを提供することも考えられなくはない。しかし、決済のニーズは経済のあらゆる場面に登場するだけに、むしろ、さまざまな領域のOSSの補完要素としての性格が強い。 たとえば、支払いのための振込みや現金の引出し・預入れなど、消費者の決済関連ニーズは、「日常の買物」というOSS領域の一部と考える方が自然だ。イトーヨーカ堂が自社店舗の顧客に対するサービスの一環として、また、ソニーが自社の消費者向けEC事業の補完要素として、決済専門の銀行を設立しようとしているのも、OSSの視点に立てば理解しやすい(注2)。 決済関連サービスは、ITの進歩にともなって、今やすっかり装置産業化してしまった。イトーヨーカ堂やソニーなどの新規参入組は、それを前提に、ITと低廉な労働力を組みあわせたビジネス・モデルを構築できる。しかも、それはあくまでも本業の補完要素であって、それ自体で利益を出そうという発想のものではない。優秀だがコストの高い人材を抱えた金融業が、それらに対抗することは容易ではない。 また、企業活動サポートの領域では、金融業以外のライバルがひしめいている。かつて、資金制約が厳しかった時代には、金融業の優位性は明らかであった。しかし、資金制約が緩み、また資金調達の手法が多様化した現在では、前述のとおり、この分野での金融業の地位は、ベンチャー・キャピタル、総合商社、コンサルティング・ファームなどと並ぶ一プレーヤーに過ぎなくなっている。 こう考えると、大部分の金融機関にとって、サービス産業としての進化の方向は、一般消費者を主力ターゲットとするOSS型の業態ということになりそうだ。 注2.その他でも、旅行代理店やスポーツ・ショップが、関連する保険商品を販売しているのは、部分的ではあるがOSSと同様の発想に立ったものと捉えられる。 6.究極は「脱・銀行」−金融流通業の構想− 消費者向けの金融OSSを実現するためには、金融商品を総合的に品揃えすることが欠かせない。とはいっても、それらの商品を製造する機能まで持つ必要はない。むしろ、商品を仕入れてきて販売するというスタイルを想定した方が自然だろう。 製造技術を持つ企業が商品の製造を担当し、販売力を持つ企業は、そこから商品を仕入れて販売に徹する。これは、通常の商品では当たり前の役割分担だが、従来の金融業のビジネスでは、こうした関係は一般的ではなかった。銀行の投信販売は、その先駆ともいえる動きである。これからは、投信だけでなく、年金、保険など、さまざまな金融商品の流通過程で、商品の「製造」と「販売」の役割分担が進むだろう。 また、預金商品でも、製造と販売の役割分担が進むものと考えられる。ペイオフ凍結が解除されれば、預金商品についても商品性、とくに信用リスクの格差が生じる。そうなると、体力がなくリスクが大きいと判断された銀行の預金商品は、他よりも高い金利を付けないと売れなくなり、その分、収益を圧迫することになる。 そうした銀行は、預金商品を自前で製造するのを諦めて、金融商品の販売に徹する方が賢明だ。これは、銀行ではなくなるということでもあるが、自前の預金商品がなくても、有力な銀行の窓口代行などの形で、預金商品を品揃えに加えることは可能だ。既存の預金は有力な銀行に移管すればよい。 その場合に問題になるのは、預金という原資を失うことになる融資の業務をどうするか、である。融資業務を続けるためには、預金を移管した先の銀行や投信などのファンドから資金を借り入れ、それを原資にしていくことが考えられる。あるいは、融資債権を他の金融機関に売却するスタイルもあるだろう。これらは、いずれにしても、金融商品の製造機能を持つ金融機関に、金融商品の素材を供給するビジネスと捉えられる。 つまり、自前の預金商品による資金調達を停止した銀行は、金融商品を販売する部門と、金融商品の素材を仕入れる部門に二分されることになる。もちろん、それらのいずれかに特化することも可能だ。 いずれにしても、製造機能を他に委ねた金融ビジネスは、金融における流通業と呼ぶことができる。この「金融流通業」こそが、大多数の金融機関にとっての進化形として想定される。この進化は、融合していた機能を分解し再編成することによって、サービスの質を高めていく動きであり、消費者のニーズにも、時代の要請にも適ったものと評価できる(注3)。 注3.信用力に不安の残る銀行に、預金業務から撤退する道を用意しておくことは、ペイオフ凍結の解除に備えるための政策としても有効だと考えられる。万一、九七年末のような大規模な資金シフトが発生した場合でも、預金の流出に見舞われた銀行が債務超過でない限りは、有力銀行への預金の移管と、それに見合う逆方向の融資の実行によって、資金流出と貸出の圧縮が連鎖するスパイラル的な信用収縮は回避できる(その際の融資については、公的資金枠をベースにした国家保証が前提となる)。逆に、こうした備えがないままにペイオフ凍結を解除すると、信用格差に応じた資金シフトが再び信用収縮につながる可能性は、依然として残っている。 7.ネット企業との競合 消費者向けの金融OSSというビジネス領域も、既存の金融業の独壇場というわけにはいかない。最大の脅威は、ITで武装したネット企業だ。ワン・トゥ・ワン・マーケティングやCRMを支援するソフトウェアなど、ITを活用すれば、少ない人員でも効率的に高度なサービスを提供することができる。既存の金融業に比べて、コスト競争力ははるかに強い。 既存の金融業は、単に品揃えを充実させて顧客の前に並べてみせるだけでは、ネット企業に対抗することは難しい。価格競争に引きずり込まれてしまえば、たとえ競争に勝ったとしても、事業の収益性は相当損なわれてしまう。既存の金融業に必要なのは、豊富なマンパワーを活かすビジネス・モデルだ。 自らのニーズを明確に特定できている顧客は、価格の安いネット企業のサービスを選択するだろう。しかし、多くの消費者は、自らの置かれた状況にもっとも適した資産設計を策定するためのサポートも必要としている。マンパワーを生かす道はここにある。 顧客の資産設計をサポートするためには、資産・負債の状況の他、所得や仕事の展望、家族の動向、さらには価値観や人生観にいたるまで、きわめて多岐にわたる情報を共有する必要がある。そうした複雑で漠然とした情報をネットでやりとりすることは困難だ。資産設計のOSSを実現するには、リアル・タイムのダイレクトなコミュニケーションを通じて、顧客との密接な関係を構築していくことが不可欠だ。 もちろん、この場合にも、ITの活用は重要なファクターとなる。ただしそれは、効率化、省力化を目的とするのではなく、あくまでも、優秀な人材のパワーを最大限に引き出すためのツールと捉えることが重要だ。 8.「三つの'C'」戦略 前項で述べた戦略は、金融業に特有なものではない。多くの小規模な専門店が、それと類似する戦略で、セルフ・サービスやチェーン・オペレーションによって効率化を進めたチェーン企業に対抗している。さらに近年では、効率化路線を採ったチェーン企業までが、効率化の果てに陥った泥沼の価格競争を抜け出すために、同様の戦略を模索している。 その戦略を、普遍的な形に整理すると、「三つの'C'」という表現でまとめることができる。三つの'C'とは、コンサルティング(Consulting)、カスタマイズ(Customize)、コミュニケーション(Communication)という、顧客と密接な関係を築くための三つの手法の頭文字を取ったものである。 コンサルティングは、顧客の潜在的なニーズを引き出すと同時に、顧客との密接な関係を築く糸口ともなる。とくに趣味的な分野で効力を発揮するが、日常生活に密着した食品スーパーでも、食材の使い方や、料理にあわせた素材の選び方など、顧客の相談に積極的に応じようという動きが広がっている。 また、カスタマイズは、顧客とともに商品・サービスを完成させる作業を通じて、顧客との関係を深めようということだ。靴や椅子、枕の最終調整、コーヒーや茶、米のブレンドなどの他、ファッションの分野で、顧客の容姿、趣味にあわせてコーディネイトしてやることも、この例に数えることができる。 三番目のコミュニケーションは、顧客のニーズを知り、関係を強化するための基本である。前述のコンサルティング、カスタマイズはその糸口としては有効だが、コミュニケーションの技術は、それを持続させるうえでの重要なポイントとなる。 三C戦略で最終的に目指すのは、サービス産業の究極の目的である第四の'C'、顧客の「コンフィデンス(Confidence=信頼)」である。顧客の信頼を勝ち得れば、不毛な価格競争に巻込まれることなく、長期にわたり安定的な取引関係を維持することも可能になる。 前項で述べた既存金融業の採るべき戦略は、まさに、この三C戦略である。顧客のニーズや悩みを聞いて、それを解決できる金融商品を提案していくのはコンサルティング。ローンも含むさまざまな金融商品を組みあわせて、顧客それぞれの資産設計を策定してやる作業はカスタマイズ。そして、人生観まで及ぶ顧客の情報を収集するには、持続的なコミュニケーションが欠かせない。 三C戦略は、コスト競争力を武器にするライバルに対抗する企業に共通の戦略だ。ネット企業との競合を考えると、既存の金融業が抱える優秀だがコストの高いマンパワーが武器となるか重荷となるかは、この三C戦略を徹底できるかどうかにかかっている。 9.おわりに−淘汰と競争の時代− 本稿の議論をまとめると、大多数の金融業の進化形として有力なのは「一般消費者を主要顧客として三C戦略を展開する金融OSS」ということになる。これは、顧客のニーズと、競合相手の戦力、方向性を考えあわせて導き出した結論だ。 とはいえ、その前提となる規制緩和の動きは、現時点ではまだまだ鈍い。現状の保護的な規制の枠組みのなかでは、「進化」という発想は出てこないかもしれない。まして、現状の安定を捨てて、それを実行に移そうとする企業はほとんどないだろう。むしろ、厳しい競争を強いることになる規制緩和に極力反対していくというのが「常識的な」選択だ。 しかし、外資系や異業種企業、新設のネット企業など、新規参入者の事業計画が消費者の支持を集めれば、その国民的なニーズに圧される形で、規制緩和は間違いなく進む。競争と淘汰のメカニズムが金融業に進化を強いる時代は確実にやってくる。 既存の金融業のうち、茹で上がる前にぬるま湯から飛び出して進化の道へ打って出る企業が、たとえ一握りでも存在するのかどうか、期待を持って見つめていきたい。 |
||
| Works総リスト |